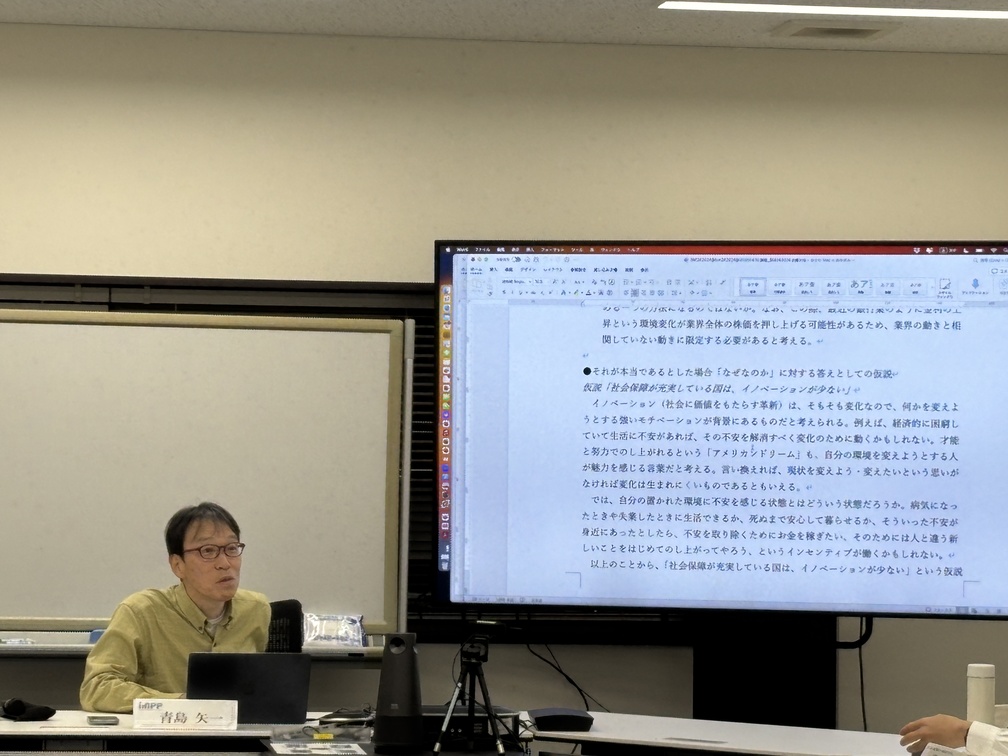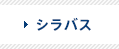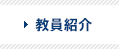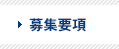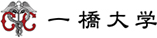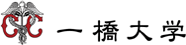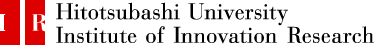2025年度「イノベーションと経営・経済・政策」②
2025年4月30日、イノベーション研究センターの青島矢一教授による「イノベーションと経営・経済・政策」第2回講義が開催されました。今回の講義は、前回提示された課題「日本ではイノベーションが停滞しているのは本当か?」という問いに立ち返るかたちで始まりました。受講生たちは、それぞれが考えてきた仮説や検証方法を共有し、講義冒頭から活発な議論が交わされました。経済統計、企業事例、制度的視点など、多様な切り口からの問いが飛び交い、問題設定への理解が一段と深まりました。
講義本編では、企業におけるイノベーション実現の核心にある「知識創造」と「資源動員」という二つの側面に焦点が当てられました。イノベーションはしばしば技術開発や商品化に限定されがちですが、青島教授はそれを「社会的な価値創出のプロセス」として再定義し、営利企業の基本活動——顧客価値の創造、生産性の向上、価値の配分——との連関性を丁寧に解きほぐしました。そこには、単なる効率性ではなく、いかに社会の中で新たな意味や便益を構築できるかという視点が強調されていました。
また、JEPLANやクリーンプラネットといった事例を通じて、不確実性の高い領域に挑む企業が、いかに周囲の信頼や支援を獲得し、事業を立ち上げていったかが示されました。この背景には、「創造的正当化(Creative Justification)」という概念が存在します。これは、経済合理性が不十分な段階でも、多様な“語り”や物語性を通じて、支援者の共感や納得を得るプロセスであり、特にイノベーションの黎明期において不可欠な動きとされます。
さらに、ソニーのFeliCa、富士フイルムのFCR開発などの大企業事例も参照され、大組織の中で新しい挑戦がいかに制度的・組織的に守られ、推進されてきたのかが議論されました。上層部の庇護や専門部門の分離、社内外ネットワークの活用などが、資源動員の具体的条件として示されました。
後半では、個人・集団・組織レベルでの知識創造のドライバーにも焦点が移りました。個人のクリエイティビティや内発的動機付け、組織内の対話・実践の場、そして「弱い紐帯」や「構造的空隙」といったネットワーク理論の視点を通して、イノベーションがいかに“人と人との関係性”に支えられているかが浮かび上がりました。
本講義を通じて明らかになったのは、イノベーションとは単なる発明や開発ではなく、「不確実性の中で意味ある資源動員を可能にする語りと関係性の構築」であるということです。学生たちは、理論と実践を横断しながら、「なぜ今イノベーションが難しいのか」、そして「それでもなぜ挑む価値があるのか」について、深い洞察を得たことでしょう。