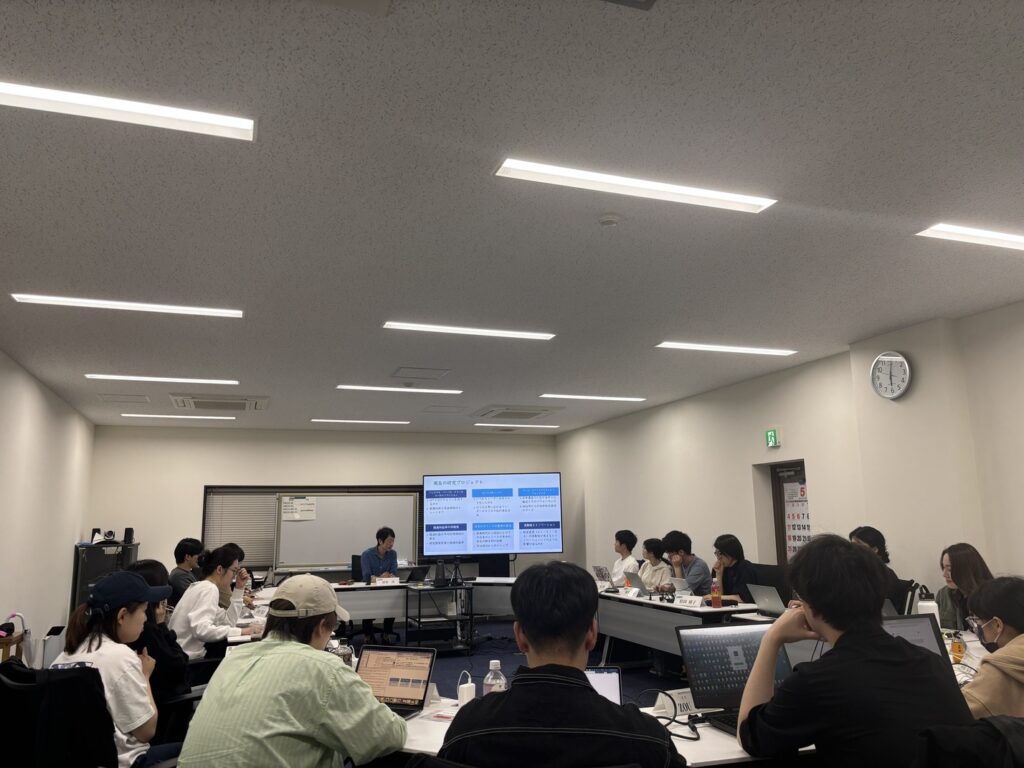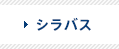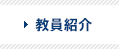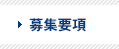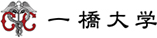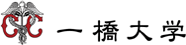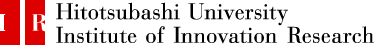2025年度「イノベーション研究方法論」②
2025年5月7日、一橋大学IMPPにおいて、早稲田大学商学学術院の清水洋教授を講師に迎え、「イノベーション研究方法論II」の第2回講義が開催されました。本講義は、社会科学における理論構築と実証検証を架橋する研究方法論を取り扱うもので、特に歴史的アプローチの意義とその活用可能性に焦点を当てた内容となりました。授業冒頭では、参加者全員が自身の研究テーマ、関心分野、想定しているデータ収集の手法について順に自己紹介を行い、それぞれの関心やアプローチの多様性が明らかとなる中、清水教授からも具体的なフィードバックがなされ、今後の研究設計に向けた議論の糸口が生まれる時間となりました。
本講義の中心的なテーマは、「歴史的アプローチが社会科学において果たしうる役割とは何か」という問いにあります。清水教授は、経営史や技術史、制度研究などにおける豊富な実践経験をもとに、歴史的アプローチの方法論的な特質を丁寧に整理しました。特に強調されたのは、以下の4点です。
第一に、時間の取り扱いの重要性です。歴史的研究において「時間」は単なる分析の枠ではなく、理論構築そのものに深く関わる概念です。因果関係の構造を把握するためには、事象の前後関係のみならず、「何がいつ起きたのか」「なぜそのタイミングだったのか」といった問いを精緻に立てる必要があります。イノベーションや制度変化の研究においても、時間的順序の明確化は仮説検証の根幹を成します。
第二に、歴史的データの性質とその活用法です。歴史的アプローチにおける「データ」とは、統計値やアンケート結果のような構造化された数値情報に限られず、時代やコンテクストに埋め込まれた多様な記述的資料を含みます。こうした資料は、単なる情報源ではなく、当時の人々が「何を重要と考え、どう語り、何を記録しなかったか」という点をも映し出す”社会的産物”であるため、その解釈には高い注意と理論的想像力が求められます。清水教授は、こうした非構造的・記述的データをいかに研究の中で「分析可能な情報単位(変数)」へと変換していくか、具体的な方法論を紹介しました。また、記述的資料を扱う上では、「何が語られ、何が語られていないか」「誰の視点が書かれており、誰の視点が欠落しているか」といった”沈黙”の読み取りも極めて重要です。歴史的データは、ある種のバイアスを前提とした素材であり、そのまま記述に引き写すのではなく、再構成的に“読む”姿勢が必要になります。
第三に、自然実験としての歴史の捉え方が紹介されました。制度変更、戦争、技術革新、外部ショックといった歴史的出来事は、現実に起きた”コントロールできない実験”とも言えます。清水教授は、「歴史は一回しか起きないから比較できない」という批判に対して、「時間を通じて事象が変化していく過程自体が比較である」と反論し、時間軸を用いた分析の可能性を強調しました。実際、多くの制度的変化や産業動態は、タイミングや文脈の違いによって異なる結果を生んでおり、そうした差異から因果推論を構築することができるという視点が提示されました。
第四に、優れた歴史研究に共通する特徴として、「説明する力」と「理論化する力」の両立があると語られました。良い歴史研究は、個別事例を丁寧に記述するだけでなく、それがどのような理論的問いと結びついているかを明確に示します。また、事例を単なる”面白い話”に留めず、比較可能性を内在させた構造へと昇華する設計が求められます。そのためには、説明対象とするメカニズムを明示すること、予想に反する結果をむしろ積極的に理論化に取り込む姿勢が重要であるとされました。
講義終盤には、参加者からも多くの質問や感想が寄せられ、特に自身の研究に歴史的アプローチを取り入れる際の注意点、制度研究との接続の方法、量的研究との併用可能性など、多様な関心に基づくやり取りが展開されました。イノベーション研究における時間の概念の扱い方、歴史データの読み解き方、そして記述と理論の接続方法に関して、改めて深く考える契機となる講義となりました。
本講義を通じて、歴史的アプローチが社会科学における厳密な理論構築に貢献しうることが、受講生一人ひとりの実感として共有される貴重な機会となりました。