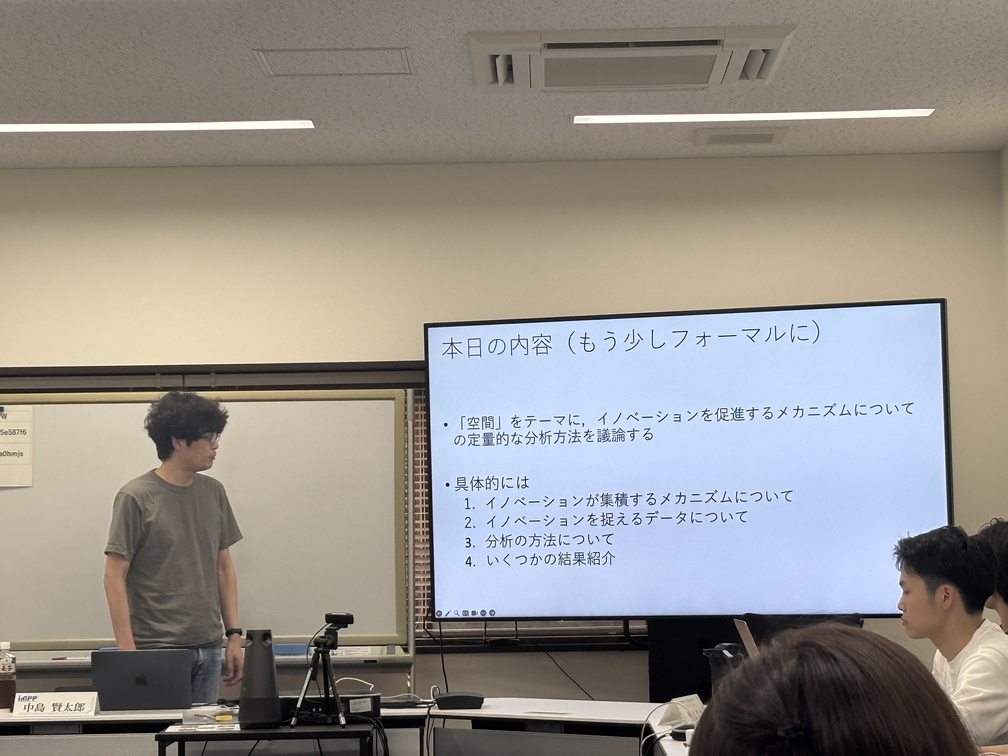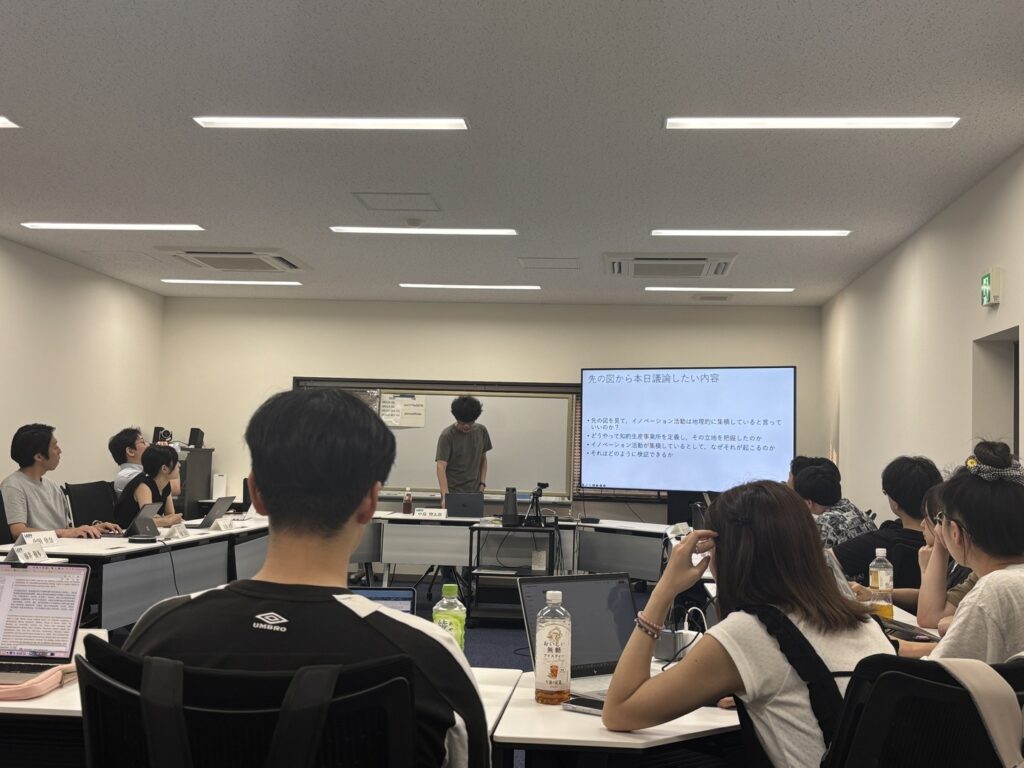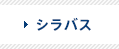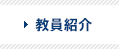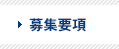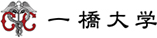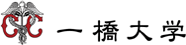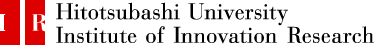2025年度「イノベーションと経営・経済・政策」⑦
2025年7月9日、「イノベーションと経営・経済・政策」第七回の講義が開催された。今回は中島賢太郎先生を講師に迎え、イノベーションの地理的集積をテーマに、特許データを活用した地理的分析を通じて、イノベーション活動の集積メカニズムを多角的に学ぶ内容となった。
講義はまず、「イノベーション活動はどこに、どのように集まっているのか」「単なる経済活動の集積とはどう異なるのか」といった問いかけから始まり、通常の産業集積とイノベーション特有の地理的特徴とを区別して捉える視点の重要性が強調された。続いて、IIP特許データベースを用いた実証分析の手法が紹介された。発明者の住所情報を地図化するためのジオコーディング技術、Rによる可視化の手順、また出願人と発明者の住所情報の差異など、実務上の分析ステップが丁寧に解説された。IIPやNBERといった異なる特許データベースの特性についても触れられ、研究設計における基盤データの選択肢が整理された。
講義の中盤では、イノベーションが特定の地域に集積する背景には、いくつかの重要なメカニズムが働いていることが紹介された。とりわけ、中島先生は「知識波及」「インプット・シェアリング」「マッチングと労働プーリング」の三点を中心に、地理的集積を支える理論的枠組みについて詳しく解説された。まず「知識波及」の観点では、優れた研究者や技術者が集まる地域において、日常的なセミナーや研究会、非公式な交流を通じて、知識やアイデアの伝播が活発に行われることが強調された。こうした“フェイス・トゥ・フェイス”のやり取りが、形式知を超えた暗黙知の共有を可能にし、結果として新たなイノベーションの芽を生み出す土壌となる。次に「インプット・シェアリング」に関しては、専門性の高いアウトソーシングサービスや中間財の供給業者が一定地域に密集することで、企業が必要とするリソースに効率よくアクセスできる環境が整うことが示された。このような環境下では、企業は自社で全てを抱える必要がなくなり、分業と専門化を通じて競争力を高めることができる。最後に「マッチングと労働プーリング」については、高度なスキルを持つ人材と、それを求める企業の双方が集まる都市部では、より望ましいマッチングが生じやすいことが説明された。特に分子生物学のようなニッチな領域では、専門性の高い人材を求める企業にとって、都市圏の厚みある労働市場が研究開発の推進力となるという具体例も紹介された。
また、特許件数や被引用件数といった定量的指標によって、ハイテク分野における空間的集中の顕著さが示された。さらに、Duranton and Overman(2005)によるK-densityアプローチが紹介され、産業ごとの空間分布の特性を捉える先行研究の知見が共有された。
本講義は、「空間」「知識」「組織」の交点でイノベーションをとらえるという新しい視点を受講生に提供するものであり、データをもとにした実証的アプローチと理論的枠組みを往復しながら、経営・政策への応用可能性を探る貴重な学びの機会となった。